2025.12.16
生活者研究
業態・企業分析
販促・マーケティング
【日本産業経済学会発表論文】日本の小売市場におけるバリュー・イノベータ ―戦略視点と消費者視点による小売業態研究-
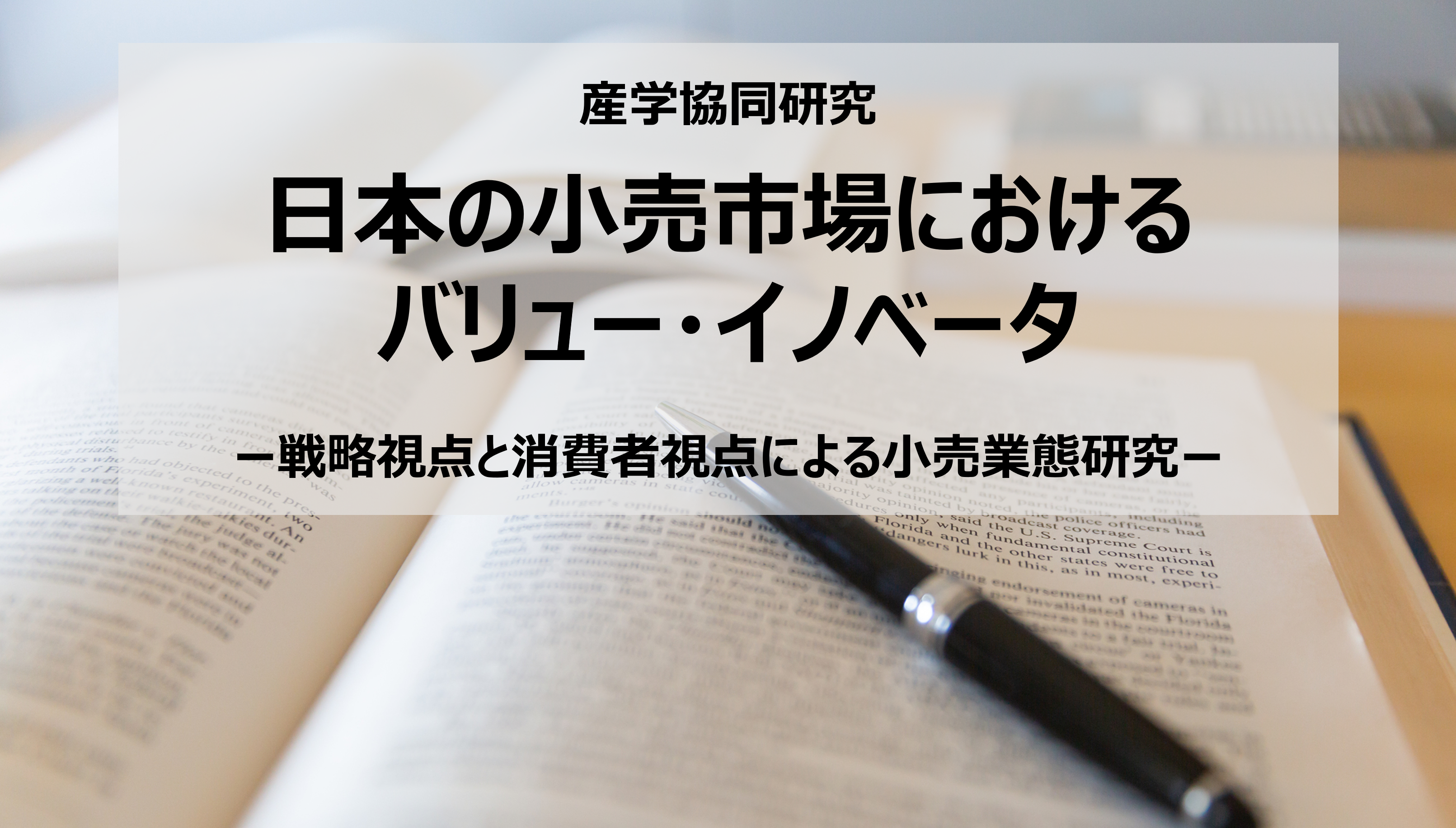
(本論文は、日本大学商学部 岸本徹也教授と株式会社クレオの産学共同研究として『日本産業経済研究』第25号(令和7年3月)へ寄稿し、2025年9月開催の日本産業経済学会第22回全国大会において奨励賞に選ばれました。)
日本の小売業界において、かつては百貨店業態などのいくつかの単独業態が優勢な状況であったが、近年ではさまざまな専門店業態が台頭することで小売業態の多様性が増している。そのような状況を捉える田村(2008)の業態盛衰モデルにおけるバリュー・イノベータとは、具体的にどのような企業でどのような顧客価値を提供しているのか、企業の戦略的視点からの企業の業績データと消費者視点からのアンケート調査の結果を踏まえてその実像を明らかにした。
1. 研究の概要
1.1 研究の背景と目的
日本の小売業界において1990年頃までは、百貨店業態、総合スーパー業態、食品スーパー業態といった一部の優勢な小売業態が業界を占める時代が続いていた。しかし近年、各種専門店業態が台頭してくることで、小売業界の多様性が増している。
小売業研究は、この小売業態の多様性を捉えていくことが重要な研究課題となっているとの認識のもと、我々は小売業界全体の動向を捉える田村(2008)の業態盛衰モデルに着目した。この業態盛衰モデルは、新業態として登場した小売企業がその後どのように盛衰していくのかの過程を表したものである(図表1)。横軸は商品の価格水準を表している。縦軸は小売業が提供する小売サービス(立地、営業時間、品揃え、接客サービス、店舗の雰囲気等)の総合的な指数として表されている。
新しい小売業態は、価格に優位性を持つ価格イノベータ、品質に優位性を持つ品質イノベータ、そしてこれらの両面に優位性を持つバリュー・イノベータとして登場する可能性が高いと考えている。価格イノベータや品質イノベータは、その後、売上の拡大を目指し市場規模の大きな覇権市場を目指し、バリュー・イノベータへと収束する可能性を想定している。
本研究の目的は、このバリュー・イノベータとは、具体的にどのような小売業で、どのようなバリューを顧客に提供しているのかについて、企業の戦略視点と消費者視点から明らかにすることである。

1.2 研究の意義
小売業に関する研究は、小売業の歴史的発展に基づき一般化を目指す小売業態研究と新しい小売業態の出現にともなうイノベーションに着目する小売イノベーション研究に大別されるが、どちらも、企業の戦略視点からのものが多い(高嶋 2007 ; 矢作 2014など)。
一方、消費者の認知的な視点から業態分類を試みる消費者視点の小売業態研究(髙橋 2014など)も増えているが、まだ企業の戦略的な視点からの研究ほど多くはない。
本研究では、この従来別々に論じられてきた企業の戦略視点と消費者視点を合わせて見ていくことで、日本の小売市場におけるバリュー・イノベータの実像を明らかにするところに研究の特徴と意義があると考えている。
本稿の構成は、この第1章に続き、第2章では、企業の戦略的な視点として企業の業績データからバリュー・イノベータの候補を探索し、第3章では、小売業態別に顧客が企業に求める価値をアンケート調査から把握する。終章となる第4章において、企業の戦略的視点と消費者視点の両方からバリュー・イノベータの実像を明らかにする。最後に残された課題について述べる。
2. 企業戦略視点:業態の変遷と市場動向
2.1 業態の流れ
小売業の変遷から業態を捉えると、大きく二つの流れがあると考えらえる。
一つは、専門化、SPA化(※1)に向かう流れである。1960年~1970年代の高度成長期における小売とは「総合小売」であり、この時代は、百貨店や総合スーパーといった一つの箱の中で衣食住の全てが揃う業態が小売のメインプレーヤーとされていた。しかし、1980年~1990年代にかけて、家具、家電、アパレル、雑貨といった各分野に特化した「専門量販店」というカテゴリーキラーが台頭するようになる。これにより、総合小売は徐々に逼迫していくのだが、総合小売、専門量販店はいずれも「大量仕入・大量販売」が前提となる業態だったため、価格競争が激化するようになっていく。この流れを受け、2000年代以降、企画・製造から販売までのサプライチェーンを内製化することで良質な商品をコストを抑えて作っていく「SPA化の時代」に入っていき、現在に至るという解釈である。
もう一つは、総合業態化、マルチ業態化への流れである。1960年~1970年代の高度成長期における「総合小売」は、1980年~現在に向かうにつれてグループ内に各種の専門業態を保有する「総合業態化」「業態多角化」へと進化を遂げていく。自ら専門業態を開発、あるいは有力業態を買収・合併することで、イオンやセブン&アイ・ホールディングス、ベイシアのような総合業態企業が発展していく。業態ポートフォリオのスクラップ&ビルドにより経営の安定化を図り、出店戦略においてはグループ業態の集中出店を取ることにより集客効果を高めるなどのシナジーを生む。さらには専門業態ごとに規模の拡大を図ることで、PB比率向上、ブランド力向上、オペレーションの効率化を進め、カテゴリーキラーである「専門量販SPA」に対抗しているという解釈である。
我々は、業態には「SPA化」と「総合業態化」という二つの流れがあると捉えたうえで、業態の変遷と市場動向を見ていき、企業の戦略視点を探っていく。
※1:ここではアパレルに限らず、企画・製造から販売までのサプライチェーンを管理するビジネスモデルである「製造小売業」全般を指す。
2.2 業態・業種別の市場規模と市場フェーズ
まず、小売業全体の市場規模を経済産業省「商業動態統計」 業種別商業販売額にて確認する(図表2)。

2023年度の小売業全体の商業販売額は164兆460億円である。1991年までは右肩上がりであったが、1991年に160兆円を超えてから現在に至るまで、小売業全体は30年以上成熟フェーズにあり、日本の人口が減少フェーズに切り替わる2008年より15年以上も前から小売業全体の市場はほぼ飽和状態にある。
これに対し、各業態および業種の市場規模推移を、各業態統計調査データをもとに整理すると、主に成長、成熟、衰退に分類することができる(図表3)。

成長市場は食品スーパー、ドラッグストア、通信販売の3業態、成熟市場はコンビニエンスストア、総合スーパー+食品スーパー、ホームセンターの3業態、衰退市場は百貨店、アパレル、家電量販店の3業態である。
そして各業態および業種を、市場規模の変遷と市場生成時期を踏まえて見ると、コンビニエンスストア、ドラッグストア、通信販売といった後発の業態ほど成長曲線が上向きであり、古くからある業態は食品を扱う業態を除き、成熟、衰退の域にあることが分かる。1990年代まではアパレル、家電、百貨店、総合スーパーが小売市場で高い占拠率にあったが、現在は、総合スーパーは引き続き維持、次いで通信販売、食品スーパー、コンビニエンスストアが高い位置にある(図表4)。

2.3 各業態の業績動向
ここからは、成長、成熟、衰退の市場から2つずつ、食品スーパー、ドラッグストア、コンビニエンスストア、ホームセンター、アパレル、百貨店の計6業態をピックアップし、直近の業績(※2)を見ながら詳細を分析していく。
まず、成長市場である食品スーパーについて各社決算資料、報道資料をもとに最新の業績をランキングすると、営業収益の上位3社はイオン系食品スーパー(営業収益3兆1035億4300万円、営業利益率1.6%)、ライフコーポレーション(営業収益8097億900万円、営業利益率3.0%)、西友(営業収益6806憶8700万円、営業利益率3.8%)である。一方で、4位のオーケー(営業収益6238億8900万円、営業利益率5.9%)と5位のヤオコー(営業収益6195億8700万円、営業利益率4.7%)は利益率が高めであるのに対し、営業収益トップのイオン系食品スーパーは利益率が上位15社内では最も低いという結果であった。
同じく成長市場であるドラッグストアおよびファーマシー(調剤薬局)は、業界再編が激しくM&Aによる経営統合が盛んであり、売上高のトップがウエルシアHD(売上高1兆2173億3900万円、営業利益率3.6%)、次いで2位がツルハHD(売上高1兆274億6200万円、営業利益率4.8%)と上位2社がイオン系列である。また、3位のマツキヨココカラ&カンパニー(売上高1兆225億3100万円、営業利益率7.4%)は、直近の業績では上位15社内で営業利益率がトップであった。
次に、成熟市場に至りつつあるコンビニエンスストアは、セブン-イレブンがチェーン全店売上高(5兆3452億4300万円)、営業総収入(8946億5900万円)、営業利益(2510億2900万円)いずれも独走している。またセブン-イレブン、ファミリーマート(チェーン全店売上高3兆692億9000万円)、ローソン(チェーン全店売上高2兆4162億9300万円)の大手3社の売上高が桁違いであり、この3社で業界を寡占している。
同じく成熟市場であるホームセンターの売上高上位3社は、カインズ(売上高5423億1700万円、営業利益率4.0%(※3) )、DCMホールディングス(売上高4886億1300万円、営業利益率5.9%)、コーナン商事(売上高4726億5400万円、営業利益率5.1%)である。ホームセンター業界は全体的に営業利益率の高い企業が多く、安定している。
そして、衰退市場にある百貨店の上位3社は高島屋(総額売上高7573億7900万円、営業利益率2.6%)、三越伊勢丹(総額売上高7047億900万円、営業利益率5.7%)、大丸松坂屋百貨店(総額売上高6854億2200万円、営業利益率3.5%)である。三越伊勢丹は営業利益率が5.7%と驚異的な回復を見せている。直近の結果を見ると、コロナ禍明けで業績が回復し、都心部展開の呉服屋系百貨店および阪急阪神百貨店(総額売上高5736億8500万円、営業利益率3.8%)が市場を牽引している。
同じく衰退市場にあるアパレルの首位はファーストリテイリング(営業収益3兆1038億3600万円)である。桁違いの営業収益で2位のしまむら(営業収益6364憶9900万円)の約5倍の営業収益である。そして3位にアダストリア(営業収益2755億9600万円)と続く。また、15位までの企業を見ると、新興系ファストファッション、つまりSPA企業の伸長と、老舗系百貨店ブランドを展開する企業の低迷が顕著であり、業界内で明暗が分かれている。
※2:各社の最新の有価証券報告書、決算短信、決算説明資料、決算補足資料、決算公告を基とする。
※3:カインズは非上場により営業利益非公開のため、営業利益率を「経常利益/営業収益」にて算出。
2.4 業態別上位3社の市場集中度と10年平均成長率
ここで、確認した6業態の上位3社の市場集中度を算出し、各業態の市場における企業の寡占度を比較したところ、低い順から、成長市場のドラッグストア(35.5%)、成長市場の食品スーパー(36.3%)、成熟市場のホームセンター(37.8%)、衰退市場の百貨店(39.6%)、衰退市場のアパレル(47.8%)、成熟市場のコンビニエンスストア(92.4%)となった。コンビニエンスストアを除き、各業態の市場における企業の寡占度は、成長、成熟、衰退に向かうほどに強まっていくことがわかる。
そこで、市場集中度の指標に基づき、6業態の上位3社がどのような経緯を踏まえて現在の位置にいるのかを把握するために、「年平均成長率 CAGR」を2014年度から2023年度の過去10年で見ていく(図表5)。

年平均成長率とは、企業の過去数年のデータをもとに、1年あたりの平均成長率を算出したものである。図表5はファーストリテイリングの直近10年間の業績を事例に算出している。なお、年平均成長率の算出にあたっては、百貨店業界は「総額売上高」ベース、コンビニエンスストア業界は「営業総収入」ベース、その他「売上高」と「営業収益(売上高+その他の営業収益)のでランキングした企業については「営業収益」ベースで算出した。
営業収益ランキングにもとづく各業態の上位3社は、ドラッグストアがウエルシアHD、ツルハHD、マツキヨココカラ&カンパニー、コンビニエンスストアはセブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、ホームセンターはカインズ、DCMホールディングス、コーナン商事、百貨店は高島屋、三越伊勢丹、大丸松坂屋百貨店、アパレルはファーストリテイリング、しまむら、アダストリアである。なお、食品スーパーの営業収益上位3社はイオン系食品スーパー、ライフコーポレーション、西友であるが、3位の西友が2021年2月までウォルマート傘下にあったことから直近2年分の決算しか公開されていないため、4位のオーケーに差し替えて見ていく。
各業態の上位3社合算による10年平均成長率は高い順からドラッグストア(7.8%)、アパレル(6.0%)、食品スーパー(5.2%)、ホームセンター(3.4%)、コンビニエンスストア(2.9%)と続き、最下位は百貨店(0.6%)である(図表6)。

概ね市場規模推移のステータスと同様に、上から成長、成熟、衰退の順に業態が並ぶ。注目すべきは、市場としては衰退フェーズにあるアパレルが上位3社においては成長率2位に位置していることである。これは、先の売上高ランキングでも言及した通り、上位がファストファッションブランドを展開する企業で占められていることが影響している。
そして、各業態の上位3社の10年平均成長率を企業別に見ると、CAGR5%以上の企業はウエルシアHD(13.8%)、ツルハHD(9.9%)、ファーストリテイリング(8.0%)、アダストリア(5.2%)、オーケー(9.2%)、イオン系食品スーパー(5.0%)、コーナン商事(5.4%)、ファミリーマート(5.1%)である(図表7)。

いずれも、SPAによるサプライチェーンの内製化や、グループシナジーを活用したPB比率の向上に力を入れている企業であるといえる。また、5%に満たないものの安定した成長率を維持する企業であるライフ(3.7%)やカインズ(3.8 %)などもPB開発およびSPA化が顕著である。
2.5 業態の変遷と市場動向まとめ
以上、各業態の市場変遷から、各業態の業績上位3社による「10年平均成長率 CAGR」までを見てきた。ここで、各業態の上位にある企業が、どのような戦略で現在の位置を維持しているかをまとめる。
SPA化を強めているのは、アパレルではファーストリテイリングやアダストリア、ホームセンターではカインズである。総合業態化によるグループシナジーを活用しPB比率を向上させているのは、ドラッグストアではウエルシアHD、ツルハHD、食品スーパー3社、ホームセンターではコーナン商事、そしてコンビニエンスストア3社である。特にイオングループはトップバリュ(食品スーパー)やハピコム(ドラッグストア)を通して、PB開発や共同購買などでグループシナジーを活かしている。また、ライフやコンビニエンスストア3社もPB比率の向上によりブランド力を高めている企業といえる。
小売企業が持続的に成長をしていくうえで、SPA化やグループシナジーを活用したPB比率の向上がカギとなるが、この「SPA化」や「PB比率向上」の流れに沿って高い売上高と成長率を維持する企業は、高いサービス品質を低価格で顧客に提供している。つまりバリュー・イノベータの「サービス品質」が高く「相対価格」が低いという概念と一致するため、「バリュー・イノベータ」の要素を有していることが推測される。
それでは、これらの企業および業態に対し、生活者はどのような価値を見出しているのか。次章からは、本章の企業戦略視点による分析と、次章の生活者視点によるイメージ分析を合わせて見ていくことで、小売業態のバリュー・イノベータが有する顧客価値を探っていく。
3. 生活者視点:顧客が小売業態に求める価値
3.1 調査概要
生活者の動向を知るにあたり、株式会社クレオと共同研究者である日本大学商学部の岸本は2024年5月に調査を実施した。業態別買物動向調査として、クレオが保有するアンケートシステム「なるほどMC.net」を利用したインターネット調査にて、全国の20歳~79歳の男女1,200名より回答を得た。調査項目は、各業態における生活者の利用実態および業態に対するイメージを把握するための設計となっている。
その中でも本研究では、生活者が小売業態に求める価値を明らかにすることを目的としていることから、各小売業態について利用したことがあると回答した者を対象に、利用業態に対して現在抱いているイメージを調査した。本研究では、利用者が業態に対して抱いている「イメージ」を業態利用における「価値」であると捉えている。
業態に対するイメージについては、田村(2001)の小売ミックスを参考とし、「アクセス」「価格」「接客」「販促」「品揃え」「雰囲気」と新たに「シーン」を加えた7つのカテゴリーで調査した。「アクセス」に入る項目は[行きやすい][何時でも利用できる][どこにでもある]、「価格」に入る項目は[高級][庶民的][値ごろ感がある][割高]、「接客」に入る項目は[親しみのある][温かみのある][無機質][誠実な]、「販促」に入る項目は[面白い][楽しい][学びがある][信頼できる]、「品揃え」に入る項目は[専門的][センスが良い][個性的][安心安全][何でもある][季節感がある][1年中変わらない]、「雰囲気」に入る項目は[活気がある][落ち着きがある][居心地が良い][先進的][伝統的]、「シーン」に入る項目は[普段使い][特別な時の利用]とした。
今回は「アクセス」と「シーン」を除いた5つのカテゴリーで分析した。理由としては、「アクセス」と「シーン」については、最寄品や買回品といった取扱商品やサービスによる影響が強く、店舗側の企業努力が及びにくい要素であると判断したからである。
なお質問項目としては、「以下の業態について、あなたがお持ちのイメージをお知らせください」という設問を立て、当てはまるものを複数選択してもらう複数回答形式を採用した。
3.2 企業成長率×顧客価値
生活者が小売業態に求める価値を明らかにするために、各業態の業績ランキング上位3社の企業成長率と顧客が各業態に対して抱いているイメージとを比較した。なお、イメージについては各業態に対しての調査だが、よく利用するチェーンとして回答者が挙げているお店が業績上位3社と同様の傾向にあるため、上位3社に対するイメージとして取り扱って問題ないと判断し、分析軸として採用している。
まずドラッグストアについては、前章でも述べた通り上位3社合算の10年平均成長率が7.8%と6業態中1位である。ドラッグストアを利用している生活者つまり顧客がドラッグストアに対して抱いているイメージの上位5項目は、「親しみのある」(22.2%)、「値ごろ感がある」(20.0%)、「庶民的」(16.8%)、「1年中変わらない」(11.9%)、「信頼できる」(10.0%)である。
次にアパレルだが、上位3社合算の10年平均成長率は6.0%と、ドラッグストアに次いで好調である。アパレルの顧客がアパレルに対して抱いているイメージの上位5項目は、「庶民的」(18.3%)、「活気がある」(15.2%)、「値ごろ感がある」(13.8%)、「専門的」(13.8%)、「楽しい」(12.6%)である。
食品スーパーは、上位3社合算の10年平均成長率が5.2%と、6業態中3位である。食品スーパーの顧客が食品スーパーに対して抱いているイメージの上位5項目は、「庶民的」(31.7%)、「親しみのある」(29.4%)、「値ごろ感がある」(24.8%)、「活気がある」(10.2%)、「信頼できる」(9.7%)である。食品スーパーは特に上位3位までの「庶民的」「親しみのある」「値ごろ感がある」に対するイメージが高いという結果が出ている。
ホームセンターは上位3社合算の10年平均成長率が3.4%と、上位3業態のドラッグストア、アパレル、食品スーパーと比べると低成長である。ホームセンターの顧客がホームセンターに対して抱いているイメージの上位5項目は、「専門的」(13.4%)が最も高く、「楽しい」(9.9%)、「居心地が良い」(9.5%)、「信頼できる」(9.4%)、「親しみのある」(9.2%)が続く。
コンビニエンスストアは、上位3社合算の10年平均成長率が2.9%と、ホームセンターと同様に低成長である。コンビニエンスストアの顧客がコンビニエンスストアに対して抱いているイメージの上位5項目は、「親しみのある」(20.9%)が最も高く、「割高」(11.0%)、「信頼できる」(9.7%)、「1年中変わらない」(9.1%)、「楽しい」(8.9%)が続く。
百貨店は、上位3社合算の10年平均成長率が0.6%と、この10年間でほぼ成長していない。百貨店の顧客が百貨店に対して抱いているイメージは、「信頼できる」(28.9%)が最も高く、「安心安全」(18.0%)、「季節感がある」(14.8%)、「センスが良い」(14.4)、「落ち着きがある」(14.3%)が続く。
ここで業態ごとの企業成長率と顧客が各業態に対して抱いているイメージとを比較し、改めて整理した(図表8)。

この結果から、売上上位3社の10年平均成長率が高い業態であるドラッグストア、アパレル、食品スーパーについては、「値ごろ感がある」「庶民的」という2つの共通の顧客イメージを持たれていることが明らかになった。このことから、「値ごろ感がある」「庶民的」は、現在の小売業態における「バリュー・イノベータ」が有する価値であると考えられる。
4. 総括
前章の結果を踏まえ、バリュー・イノベータであると考えられるドラッグストア、アパレル、食品スーパーにおける10年平均成長率の高い上位3社について、再度顧客イメージを整理した(図表9)。

これらの企業が共通で有する顧客イメージ、つまり共通価値は「値ごろ感がある」と「庶民的」の2つである。このことから小売業態の成長において、「値ごろ感がある」、つまり提供する商品・サービスが納得できる品質と価格であることと、「庶民的」、つまりサービスや価格が広く多くの人にとって利用しやすいものであることの2点が、小売業態の成長にとって重要な顧客価値であると考えられる。
また、それぞれに対して個別に抱かれている顧客イメージ、つまり個別価値もある。ドラッグストアは「親しみのある」「1年中変わらない」「信頼できる」、アパレルは「活気がある」「専門的」「楽しい」、食品スーパーは「親しみのある」「活気がある」「信頼できる」のそれぞれ3つである。ドラッグストアと食品スーパーでは「親しみのある」「信頼できる」の2項目で共通性が見られた。アパレルと食品スーパーでは「活気がある」の1項目において共通性が見られた。これらはそれぞれの企業における商品やサービスに必要な個別価値であることが推測される。
そして、これらの顧客価値を、田村(2008)の業態盛衰モデルに当てはめたのが図表10である。

バリュー・イノベータには「値ごろ感がある」と「庶民的」の2つの共通価値があった。そしてこの価値は、各業態の変遷と各業態の成長企業が取る戦略とを鑑みるに、SPA化やグループシナジーを活用したPB比率の向上化を推進したからこそ提供できたといえる。また、「値ごろ感がある」と「庶民的」はつまり、広く多くの顧客のニーズを満たしているということであり、「覇権市場の支配的企業」に近しい価値を有しているといえる。
さらに、バリュー・イノベータは共通価値に加えて、それぞれの企業における商品やサービス、利用シーンに合わせて求められる個別価値を有している。その中で、ドラッグストアと食品スーパーは「親しみのある」「信頼できる」の2項目で共通性があった。両方とも、食品や日用品などの生活必需品、つまり最寄品を取り扱っており、日常的な利用がなされているという点が、共通の個別価値を有するに至る背景となっていると考えられる。利用頻度の高いお店だからこそ親しみが求められ、毎日使う商品を買うからこそ信頼できるお店から信頼できるものを買いたいという顧客ニーズがあり、それこそが価値になっていると考えられる。
一方でアパレルにおいては、「専門的」「楽しい」の2項目がアパレルだけの個別価値であった。アパレルが取り扱う服飾品は買回品のため、比較検討の過程で差別化につながる専門性や選ぶ楽しさといった点が求められており、それがドラッグストアや食品スーパーにはない独自の価値になっていると考えられる。
なお、アパレルに関しては、業態全体の市場が衰退でありながらファストファッション企業に関しては成長フェーズにある点が注目である。1990年頃までのアパレル業界は百貨店ブランドが中心となっており、服飾品はハレの買い物という位置づけだった。しかし現在ではファストファッション企業が市場の上位を占めている。このことからも、生活者はハレや特別感を持てる価値よりも、値ごろ感や庶民的といったバリュー・イノベータが有する価値を求めるようになってきたことが推察される。
現在、生活者は買い物に対してハレや特別感よりも日常の中での小さな楽しみを求めるようになってきている。ゆえに、「値ごろ感がある」「庶民的」という価値は小売業態にとって今後、より重要なポイントとなっていくかもしれない。
今後は、生活者にとっての買い物が日々の生活においてどのような位置づけに変化していくのか、その変化に伴い求められる小売業態の価値とは何なのか、といった点を研究課題としていきたい。
参考文献
- 高嶋克義(2007)「小売業態革新に関する再検討」『流通研究』9(3), 33-51.
- 髙橋広行(2014)「消費者視点のリテール・ブランド・エクイティ」『マーケティングジャーナル』33(4), 57-74.
- 田村正紀(2001)『流通原理』千倉書房。
- 田村正紀(2008)『業態の盛衰』千倉書房。
- 矢作敏行(2014)「小売事業モデルの革新論−分析枠組の再検討」『マーケティングジャーナル』33(4), 16-28.
- 経済産業省 「商業動態統計」 業種別商業販売額(FY1980~FY2023)
- 経済産業省 「商業動態統計」 百貨店・スーパー商品別販売額(FY1980~FY2023)
- 日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)「ドラッグストア実態調査」(FY2000~FY2023)
- 日本通信販売協会(JDMA)「通信販売市場売上高調査」(FY1997~FY2023)
- 日本フランチャイズチェーン協会 「フランチャイズチェーン統計調査」(1983~2023)
- 日本DIY・ホームセンター協会 「年間総売上高」(FY1973~FY2023)
- 日本百貨店協会 「百貨店売上高」(1974~2023)
- 「日本の小売業1000社ランキング2024」ダイヤモンド・チェーンストア 2024-09-15
- 「小売業調査 第48回~第57回」日経MJ 2015年7月~2024年7月記事
- 「百貨店業績ランキング」繊研新聞 2024-07-26
他、各業態の業績については、各社決算資料、決算公告を出典先として参照。
岸本徹也・水野明美・河野智子・芦田有紀子(2025)「日本の小売市場におけるバリュー・イノベータ ―戦略視点と消費者視点による小売業態研究-」『日本産業経済研究』第25号(令和7年3月)を転載
引用に関する注意事項
本論文について、引用の際は出典を明記ください。
<記載例>
引用:岸本・水野・河野・芦田(2025)
出典:岸本徹也・水野明美・河野智子・芦田有紀子(2025)「日本の小売市場におけるバリュー・イノベータ
―戦略視点と消費者視点による小売業態研究-」『日本産業経済研究』第25号(令和7年3月)


